2015年08月17日
早く涼しくならないかなあ
誕生日のお祝いに「ハンチング帽」をもらいました。

ちょっと今すぐに被ることはできません。
私は普段もハンチングを被っているので、早く被りたいものです。
早く涼しくならないかなあ

ちょっと今すぐに被ることはできません。
私は普段もハンチングを被っているので、早く被りたいものです。
早く涼しくならないかなあ
2015年08月15日
提灯の灯ろう
昨晩春日大社で提灯を売っていました。
最近読んだ「しゃばけ」という小説の中で、真っ暗闇の江戸の街(お茶の水辺り)を提灯だけを頼りに主人公の一太郎が歩いて行く描写がありますが、真っ暗闇の中提灯だけを頼りに歩くというのはどんな感じなのだろう、一度経験してみたいと思っていたところなので、提灯を買ってみました。
巫女さんが提灯の針金を棒にくるくるっと巻いて、灯を入れてくれます。
これを見た私は、家に帰ってから、この針金を取って吊り下げれば、回り灯籠のようになり、電気を消して真っ暗にすれば、「結構行けるんじゃないかなあ。」と思い、喜びました。
提灯として使っている間は、残念ながら真っ暗闇ではないので、一太郎のような経験はできませんでした。
しかし家に帰ってすぐに針金を棒から外し、灯を入れて吊り下げてみました。


これを見ているだけで、何か涼しくなって来るような気がします。
翌日明るいところで撮った写真です。

最近読んだ「しゃばけ」という小説の中で、真っ暗闇の江戸の街(お茶の水辺り)を提灯だけを頼りに主人公の一太郎が歩いて行く描写がありますが、真っ暗闇の中提灯だけを頼りに歩くというのはどんな感じなのだろう、一度経験してみたいと思っていたところなので、提灯を買ってみました。
巫女さんが提灯の針金を棒にくるくるっと巻いて、灯を入れてくれます。
これを見た私は、家に帰ってから、この針金を取って吊り下げれば、回り灯籠のようになり、電気を消して真っ暗にすれば、「結構行けるんじゃないかなあ。」と思い、喜びました。
提灯として使っている間は、残念ながら真っ暗闇ではないので、一太郎のような経験はできませんでした。
しかし家に帰ってすぐに針金を棒から外し、灯を入れて吊り下げてみました。


これを見ているだけで、何か涼しくなって来るような気がします。
翌日明るいところで撮った写真です。

2015年08月15日
春日大社の万燈籠と東大寺
昨晩春日大社の万燈籠に行ってきました。
春日大社ははじめてなのですが、広々とした境内に沢山の神社が祀ってあり、中々のものです。
正門を入って右側の広場に沢山並べられた灯篭は幻想的で圧巻です。



昨晩は最終日とあって、沢山の人で賑わい、長蛇の列に交じって進んで行きました。
本殿の中にお社が15あり、「若宮15社めぐり」というのだそうですが、その間の廊下に吊り下げられた沢山の燈籠に灯が入っており、暗闇の中目を楽しませてくれます。








東大寺は午後7時を回ると入場料がただになるので、春日大社を出て東大寺に回りました。
昼間に見る東大寺とはまったく違う景色を見ることができます。

正面の2階に窓が開いていて、中の大仏様が見えるのが分かりますか?



外に出ると、東大寺の建物が池に映っています。

春日大社ははじめてなのですが、広々とした境内に沢山の神社が祀ってあり、中々のものです。
正門を入って右側の広場に沢山並べられた灯篭は幻想的で圧巻です。
昨晩は最終日とあって、沢山の人で賑わい、長蛇の列に交じって進んで行きました。
本殿の中にお社が15あり、「若宮15社めぐり」というのだそうですが、その間の廊下に吊り下げられた沢山の燈籠に灯が入っており、暗闇の中目を楽しませてくれます。
東大寺は午後7時を回ると入場料がただになるので、春日大社を出て東大寺に回りました。
昼間に見る東大寺とはまったく違う景色を見ることができます。
正面の2階に窓が開いていて、中の大仏様が見えるのが分かりますか?

外に出ると、東大寺の建物が池に映っています。
2015年08月09日
貨物列車
JR立花駅から10分ほどの所に神戸地裁尼崎支部があります。
先日そこの帰りに、駅のホームで待っていると、長いコンテナカーの列が通り過ぎました。
東海道線のためなのでしょうか、ホームで待っている時に結構通過します。
冬などは、寒い大きな風がドッと吹き抜けます。
しかしコンテナカーの列は殺風景ですネー、味気ない。
むかしは貨物列車の最後には車掌車が付いており、郵便車が付いていることもあり、味がありましたネー。





いずれもウィキペディアより
ちょっとウィキペディアで調べてみました。
貨(物)車と貨物列車の違いは分かりますか?
前者は単体で後者は字の如く列車です。そんなことも知らなかった。
その外に荷物列車や新聞列車というのもあります。
荷物列車の解説の個所で、鉄道小荷物、鉄道手荷物という記載がありました。
それを読むと、東京での司法修習(昭和53年4月から7月までと54年10月から55年3月まで)の際これを利用したのを思い出しました。
ウィキペディアでは、1929年に始まり、ピークが1963年の1億5837万個で、1984年には3745万個に落ち込み、1986年(昭和59年)に終了したとありますから、間違いありません。
布団袋に布団と必需品など身の回りの物を詰め込み、国鉄のトラックで取りに来てもらい、松戸の寮で受け取ったのを覚えています。
当時は引越し屋さんもなければ宅配便もありませんでしたね。
小説などでも、リアカーで荷物を近くの駅に運んでいる描写があります。
そして受取証である(鉄道)チッキという言葉もありました。
ちなみに列車の区別と種類はおおよそ次のようです。
旅客車(客車、手荷物車、混合車)、貨(物)車(有蓋貨車(有蓋車、鉄製有蓋車、鉄側有蓋車、冷蔵車、通風車、家畜車、豚積車、活魚車、陶器車、家禽車)、無蓋貨車(無蓋車、長車、コンテナ車、大物車、車運車、土運車)、タンク貨車(タンク車、水運車)、ホッパー車、事業用貨車(郵便車、車掌車、雪掻車、歯車車など))。
先日そこの帰りに、駅のホームで待っていると、長いコンテナカーの列が通り過ぎました。
東海道線のためなのでしょうか、ホームで待っている時に結構通過します。
冬などは、寒い大きな風がドッと吹き抜けます。
しかしコンテナカーの列は殺風景ですネー、味気ない。
むかしは貨物列車の最後には車掌車が付いており、郵便車が付いていることもあり、味がありましたネー。





いずれもウィキペディアより
ちょっとウィキペディアで調べてみました。
貨(物)車と貨物列車の違いは分かりますか?
前者は単体で後者は字の如く列車です。そんなことも知らなかった。
その外に荷物列車や新聞列車というのもあります。
荷物列車の解説の個所で、鉄道小荷物、鉄道手荷物という記載がありました。
それを読むと、東京での司法修習(昭和53年4月から7月までと54年10月から55年3月まで)の際これを利用したのを思い出しました。
ウィキペディアでは、1929年に始まり、ピークが1963年の1億5837万個で、1984年には3745万個に落ち込み、1986年(昭和59年)に終了したとありますから、間違いありません。
布団袋に布団と必需品など身の回りの物を詰め込み、国鉄のトラックで取りに来てもらい、松戸の寮で受け取ったのを覚えています。
当時は引越し屋さんもなければ宅配便もありませんでしたね。
小説などでも、リアカーで荷物を近くの駅に運んでいる描写があります。
そして受取証である(鉄道)チッキという言葉もありました。
ちなみに列車の区別と種類はおおよそ次のようです。
旅客車(客車、手荷物車、混合車)、貨(物)車(有蓋貨車(有蓋車、鉄製有蓋車、鉄側有蓋車、冷蔵車、通風車、家畜車、豚積車、活魚車、陶器車、家禽車)、無蓋貨車(無蓋車、長車、コンテナ車、大物車、車運車、土運車)、タンク貨車(タンク車、水運車)、ホッパー車、事業用貨車(郵便車、車掌車、雪掻車、歯車車など))。
2015年08月01日
京橋界隈
5月以来3か月ほど間が空いてしまいました。 その間、マイナンバー法を含めた個人情報保護法に関する講演会を3回ほどしたことや仕事が多忙であった、というよりか精神的に余裕がない状態が続いたといった方が正確です。
今日は午後2時に仕事の関係で城東区新喜多にあるお宅を訪問して面談をしていました。
京橋駅付近には商店街の入り口が数本あるのがホームなどから見えており、一度行ってみたいと思っていましたので、そのお宅はJR京橋駅南口を出て15分ほど歩いた所だったのですが、帰りにフラフラと歩きまわりました。
京橋駅南口を出て学研都市線(旧片町線)の南側はまだ古い建物などが残っており、オーという感じでした。

煙突が見えたので、そばまで行ってみました。
明らかに古い工場跡です。



裏側、今はこちらが表なのでしょうが、にも古い古城跡に会社名の看板が張り付けてあり、その横にはレンガ造りの壁に新しい会社名のプレートがありました。


会社の名前もレトロな感じがしますねー。
連れ込み旅館と思しき旅館や廃屋となった歯医者さんもありました。


また路上に屋台を出して、一杯できるお店があり、なんと人でいっぱいでした。


如何にも昭和の下町を思い浮かべます。
うれしいのは、道路にアスファルトがなく、土やぺんぺん草が見えていることです。
この辺りを歩いていると、小さい頃に総武線の新小岩や市川辺りに連れて行かれたことを彷彿とさせられます。
ビックリしたのは、京橋駅南口のスグ横に慰霊碑の仏像があることです。



その説明書きによれば、終戦の前日である8月14日にB29の空襲があり、片町駅に避難していた人が被災したとあります。
その数、氏名の判明している人だけでも200数十名、氏名のわからない人を含めると400から500人もいるそうです。
あと24時間もすれば、決してそんな目に会わなかったはずなのに、そこに居られた人はその瞬間どんな思いだったのでしょうか?
戦争は、決して歴史の表には表れない悲劇をそこかしこに残して行くものです。
京橋駅の東側に入り口のある商店街へ入って行きました。
JR天満駅北側のドヤドヤした感じですが、天満駅北側に比べると道幅が広いので、少しユッタリとした感じです。
「中華そば」屋さんもあります。

うれしかったのは、「昭和ロマンの香る街 さくら通り」という看板のある狭い商店街があり、そこには色々な飲食店(焼肉と韓国料理が多かった)と連れ込み旅館もありました。






1号線の北側に入り口のある商店街へも入ってみました。
入り口付近はドヤドヤした感じですが、途中からは普通にある(例えばJR桃谷駅の東側の商店街)ような街並みで、色々なお店があるのを見て歩くのは楽しい感じです。


1時間以上歩き回ったので、珈琲館で休憩を取りましたが、そのすぐ前にレストランがありました。
レストランといってもカウンターだけの狭いお店で、フライものを主とし、表で揚げたフライなどをテイクアウトできるようになっています。
私もそこで夕食用に「ドビカツ丼」を買い求めました。

駅前まで戻って来ると、あの有名な「グランシャトウー」がありました。


東西線に乗るため、南口に向かったのですが、どう見ても古い工場か何かの後に残ったレンガ造りの壁を利用した建物があり、これも中々味のあるものでした。



ちょっと力を入れすぎて書きましたかねー。 果たして続けることができるだろうか?
今日は午後2時に仕事の関係で城東区新喜多にあるお宅を訪問して面談をしていました。
京橋駅付近には商店街の入り口が数本あるのがホームなどから見えており、一度行ってみたいと思っていましたので、そのお宅はJR京橋駅南口を出て15分ほど歩いた所だったのですが、帰りにフラフラと歩きまわりました。
京橋駅南口を出て学研都市線(旧片町線)の南側はまだ古い建物などが残っており、オーという感じでした。

煙突が見えたので、そばまで行ってみました。
明らかに古い工場跡です。



裏側、今はこちらが表なのでしょうが、にも古い古城跡に会社名の看板が張り付けてあり、その横にはレンガ造りの壁に新しい会社名のプレートがありました。


会社の名前もレトロな感じがしますねー。
連れ込み旅館と思しき旅館や廃屋となった歯医者さんもありました。


また路上に屋台を出して、一杯できるお店があり、なんと人でいっぱいでした。


如何にも昭和の下町を思い浮かべます。
うれしいのは、道路にアスファルトがなく、土やぺんぺん草が見えていることです。
この辺りを歩いていると、小さい頃に総武線の新小岩や市川辺りに連れて行かれたことを彷彿とさせられます。
ビックリしたのは、京橋駅南口のスグ横に慰霊碑の仏像があることです。



その説明書きによれば、終戦の前日である8月14日にB29の空襲があり、片町駅に避難していた人が被災したとあります。
その数、氏名の判明している人だけでも200数十名、氏名のわからない人を含めると400から500人もいるそうです。
あと24時間もすれば、決してそんな目に会わなかったはずなのに、そこに居られた人はその瞬間どんな思いだったのでしょうか?
戦争は、決して歴史の表には表れない悲劇をそこかしこに残して行くものです。
京橋駅の東側に入り口のある商店街へ入って行きました。
JR天満駅北側のドヤドヤした感じですが、天満駅北側に比べると道幅が広いので、少しユッタリとした感じです。
「中華そば」屋さんもあります。

うれしかったのは、「昭和ロマンの香る街 さくら通り」という看板のある狭い商店街があり、そこには色々な飲食店(焼肉と韓国料理が多かった)と連れ込み旅館もありました。






1号線の北側に入り口のある商店街へも入ってみました。
入り口付近はドヤドヤした感じですが、途中からは普通にある(例えばJR桃谷駅の東側の商店街)ような街並みで、色々なお店があるのを見て歩くのは楽しい感じです。


1時間以上歩き回ったので、珈琲館で休憩を取りましたが、そのすぐ前にレストランがありました。
レストランといってもカウンターだけの狭いお店で、フライものを主とし、表で揚げたフライなどをテイクアウトできるようになっています。
私もそこで夕食用に「ドビカツ丼」を買い求めました。

駅前まで戻って来ると、あの有名な「グランシャトウー」がありました。


東西線に乗るため、南口に向かったのですが、どう見ても古い工場か何かの後に残ったレンガ造りの壁を利用した建物があり、これも中々味のあるものでした。



ちょっと力を入れすぎて書きましたかねー。 果たして続けることができるだろうか?


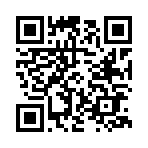
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





